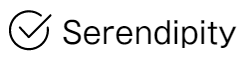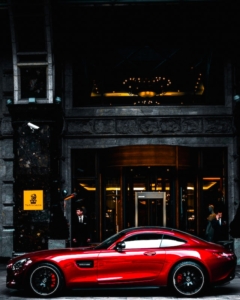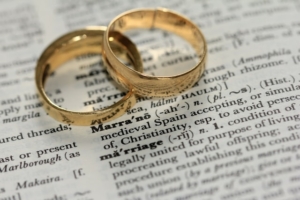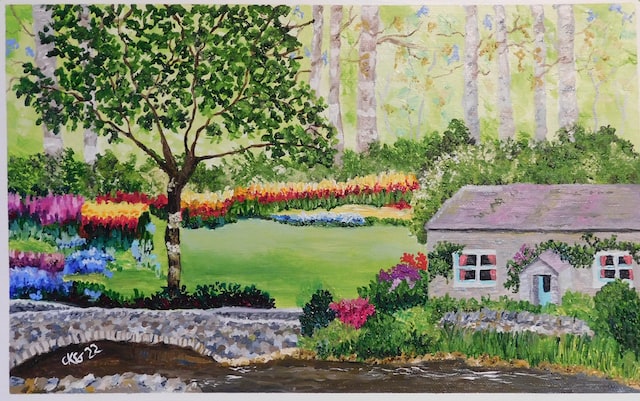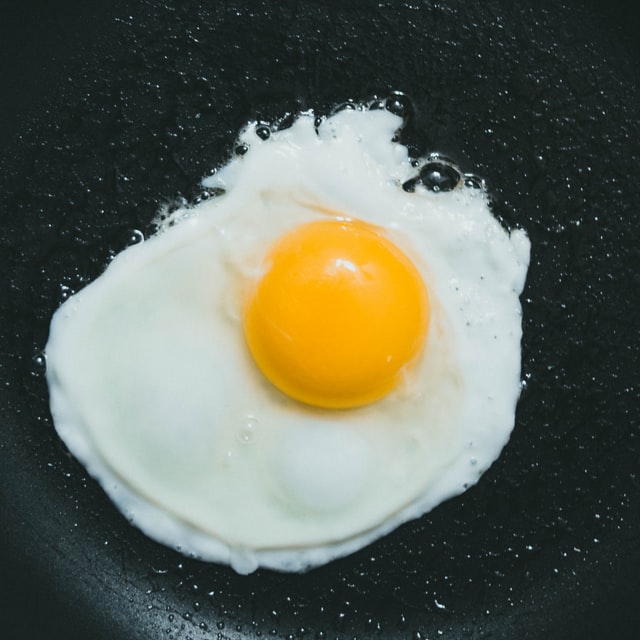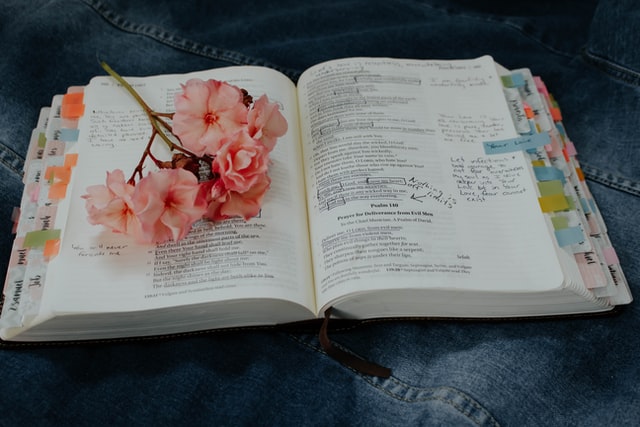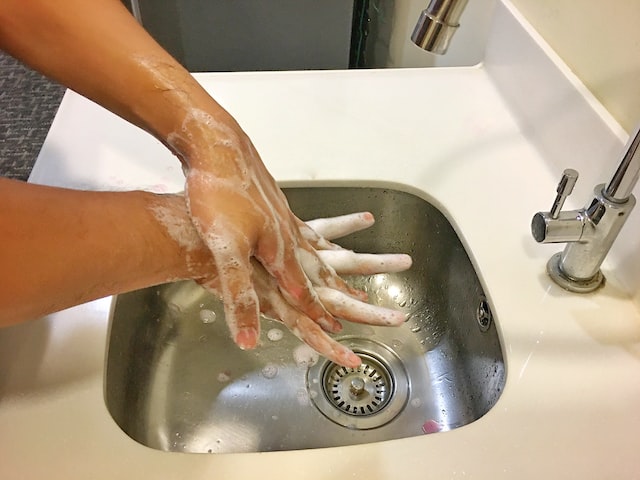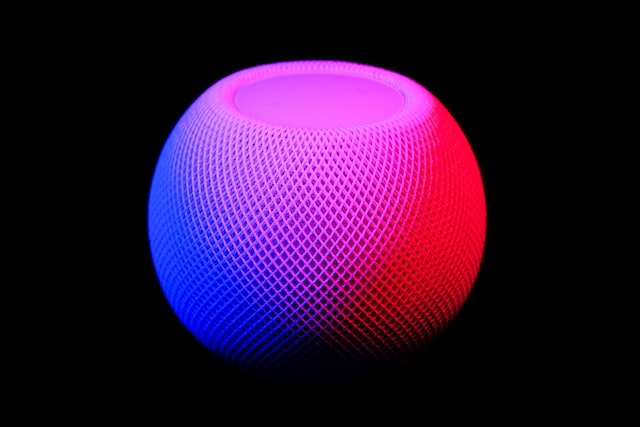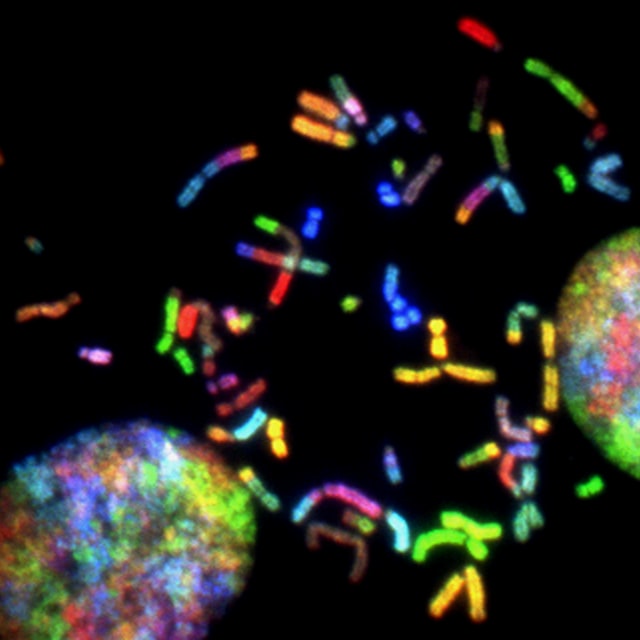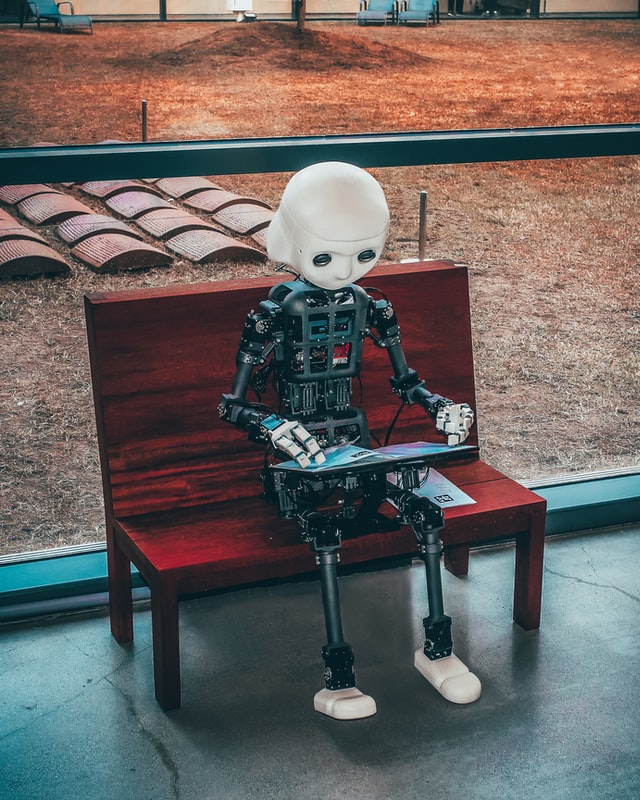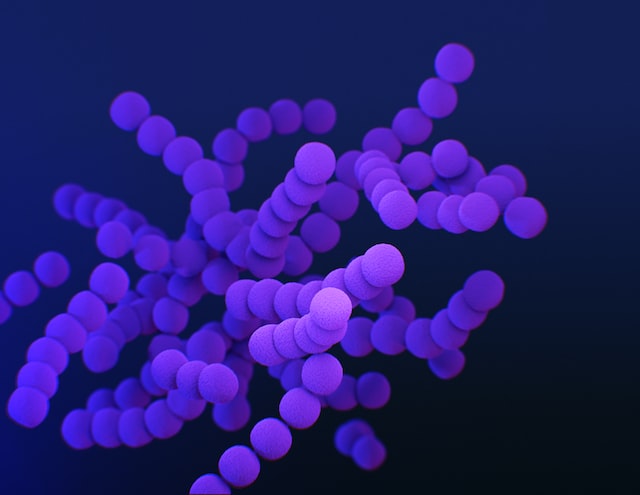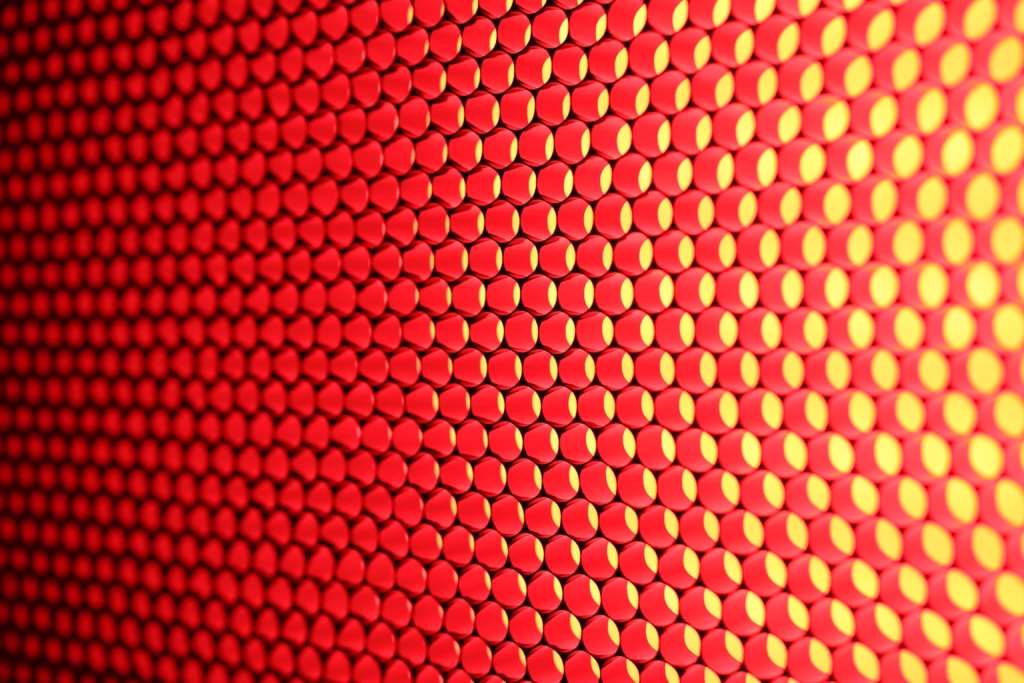新着記事
道徳的な行動は報われる
互恵性の論理(誰もが助け合えば、全員が利益を得られる)が世に公表されて久しいです。が、それを実践している人は少ないかもしれません。
One of the most fundamental questions facing humanity is: why do we behave morally?
参照元:https://www.mpg.de/19486973/evolution-of-moral-norms
– マックス・プランク研究機構 Max-Planck-Gesellschaft. NOVEMBER 11, 2022 –
無私の行動や協力は、当然というわけにはいきません。
マックス・プランク数学研究所(現マックス・プランク動物行動研究所)のモハマッド・サラシュア氏は、ゲーム理論に基づくアプローチを用いて、個人が利己主義を脇に置くことになぜ価値があり得るのかを明らかにしました。
人類が直面している最も根本的な問題のひとつは、「なぜ人は道徳的な行動をとるのか」ということです。
なぜなら、ある状況下で、私たちが自己の利益を脇に置き、集団のために–時には自己犠牲を払ってまで–身を投じていることは決して自明のことではないからです。
この道徳的な難問を解決するために、多くの理論が開発されてきた。よく知られているのは、共通の遺伝子が生き残るように個人が親族を助けるというもの(血縁淘汰)と、「あなたが私の背中をかけば、私もあなたの背中をかきます」という原則が適用されるというものです。
人々が互いに助け合えば、最終的には誰もが利益を得ることができます(互恵性の原理)。
囚人のジレンマと協調ゲームとの組み合わせ
ドイツのライプチヒにあるマックス・プランク数学研究所の数学者モハマッド・サラシュール氏は、道徳規範の出現を説明するためにゲーム理論のツールを使っています。
サラシュア氏にとって、最初の疑問は、そもそもなぜ道徳的規範が存在するのか、ということでした。
そして、なぜ私たちは異なる、あるいは対照的な道徳規範を持つのでしょうか。
例えば、「他人を助けなさい」という規範は自己犠牲的な行動を促すが、服装規定などの規範は利己主義の抑制とはあまり関係がないように見えます。
1つ目は、古典的な囚人のジレンマで、2人のプレイヤーが、小さな報酬のために協力するか、より大きな報酬のために裏切るか(社会的ジレンマ)を決めなければならないゲームです。
このゲームは、社会的ジレンマの典型的な例であり、集団全体の成功のためには、個人が無私の行動をとることが要求されます。
このゲームでは、全員が利他的に行動するシナリオに比べ、利己的に行動するメンバーが多ければ全員が損をします。
しかし、少数の個人が利己的に行動すれば、利他的なチームメンバーよりも良い結果を受け取ることができます。
第2に、調整作業、資源の分配、リーダーの選択、紛争解決など、グループ内の典型的な意思決定に焦点を当てたゲームです。
これらの問題の多くは、最終的に調整問題または反調整問題に分類されます。
2つのゲームをカップリングしなくても、囚人のジレンマでは、協力しても報われず、無私の行動をとる人が十分にいれば、個人の立場からは利己的な行動が最良の選択であることは明らかです。
しかし、利己的に行動する個人は、調整問題を効率的に解決することができず、活動の調整に失敗して多くの資源を失うことになります。
2つのゲームの結果を全体として考え、協力に有利な道徳的規範が働いている場合、状況は全く異なるものになります。
今、囚人のジレンマにおける協力は、2番目のゲームでの利益が1番目のゲームでの損失を補って余りあるため、突然、利益を生むことがあります。
利己主義から協調・協力へ
このプロセスの結果、協力的な行動だけでなく、社会秩序も出現します。
すべての個体がそこから利益を得る–そしてこのために、道徳的な行動は彼らにとって報われるのです。
サラシュア氏:私の進化モデルでは、最初は無私の行動はありませんでしたが、2つのゲームの結合の結果、より多くの道徳的規範が出現しました。それから、私は、多くの協力があるシステムへの突然の移行を観察しました。 この「道徳的状態」では、個人が活動をよりよく調整するのに役立つ一連の調整規範が発展し、まさにこれを通じて社会規範や道徳基準が出現し得るのです。しかし、調整規範は協力に有利であり、協力は個人にとっても報われる行動であることがわかります。
道徳的な制度はトロイの木馬のように振る舞う。秩序と組織を促進するために個人の自己利益からいったん確立されると、それはまた自己犠牲的な協力をもたらすのです
サラシュア氏は仕事を通じて、社会の仕組みをより深く理解したいと考えています。
サラシュア氏:これは、将来的に人々の生活を向上させるのに役立ちます。しかし、私のゲーム理論的アプローチは、ソーシャルメディアにおける社会規範の出現を説明するのにも使えます。そこでは、人々は情報を交換すると同時に、戦略的な意思決定を行っています–たとえば、誰を支持するか、どんな大義を支持するか、などです。ここでも、情報の交換と協力的な戦略の出現という2つの力学が同時に働いているという。しかし、ゲーム理論がこの問題にも新しい光を当ててくれるかもしれません。


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
関連記事
新着記事
-

 男女ともに長生きになる「男女平等」2023.03.07健康
男女ともに長生きになる「男女平等」2023.03.07健康 -

 他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く2023.03.06人体・脳
他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く2023.03.06人体・脳 -

 「寿命を延ばす」良質な睡眠2023.03.05健康
「寿命を延ばす」良質な睡眠2023.03.05健康 -

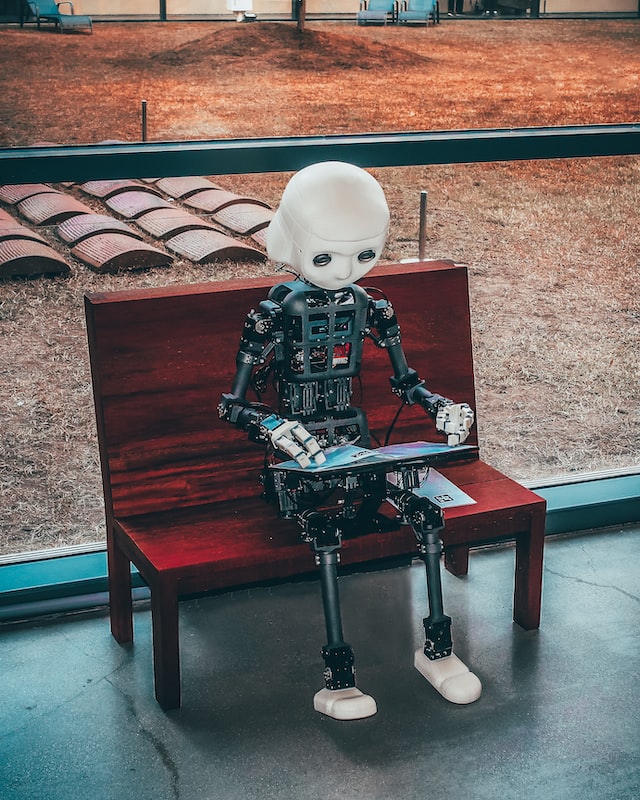 見極める力を養う「チャットボットの精度」2023.03.04技術
見極める力を養う「チャットボットの精度」2023.03.04技術 -

 健康増進と生きがいにつながる「森林浴」2023.03.03健康
健康増進と生きがいにつながる「森林浴」2023.03.03健康 -

 米国の6人に1人「肥満による死」2023.03.02健康
米国の6人に1人「肥満による死」2023.03.02健康 -

 週休4日制で生産を維持する2023.03.01社会
週休4日制で生産を維持する2023.03.01社会 -

 オンライン学習で学生に届く教育方法2023.02.28学習
オンライン学習で学生に届く教育方法2023.02.28学習 -

 学業成績に影響を与える「夜間の睡眠」2023.02.27健康
学業成績に影響を与える「夜間の睡眠」2023.02.27健康 -

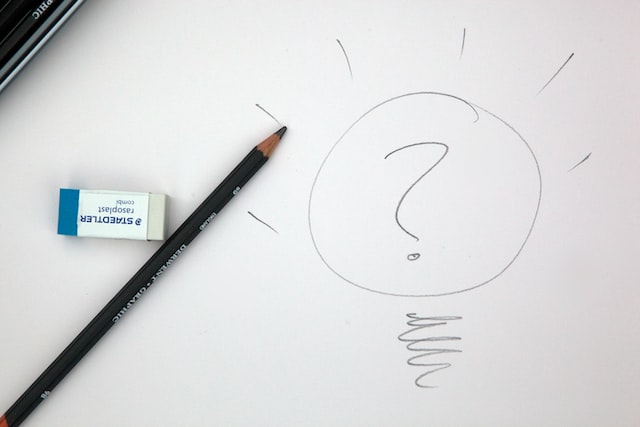 心の豊かさに大きく影響を与える「目的意識を持った10代の若者」2023.02.26健康
心の豊かさに大きく影響を与える「目的意識を持った10代の若者」2023.02.26健康
よく読まれている記事
-

 なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか
なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか -

 どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」
どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」 -

 視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」
視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」 -

 「触覚が敏感な部位はなぜあるのか」触覚メカニズムが解明される
「触覚が敏感な部位はなぜあるのか」触覚メカニズムが解明される -

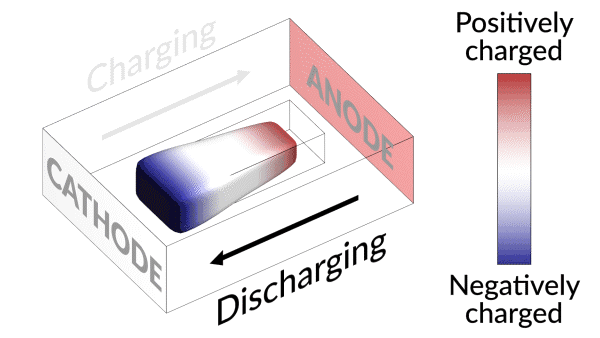 不活性化されたリチウムイオン電池を甦えさせる「復活するリチウムイオン電池」
不活性化されたリチウムイオン電池を甦えさせる「復活するリチウムイオン電池」 -

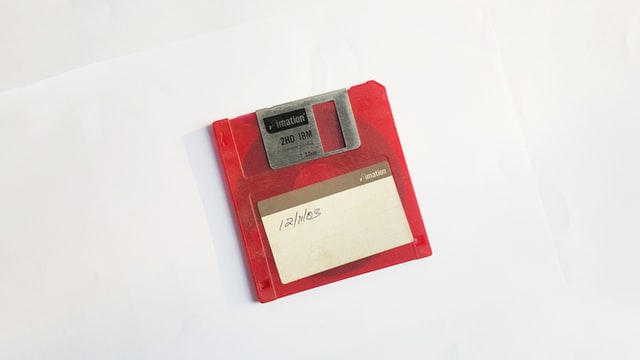 記憶が脳に保存される新しい理論「MeshCODE理論」が開発される
記憶が脳に保存される新しい理論「MeshCODE理論」が開発される -

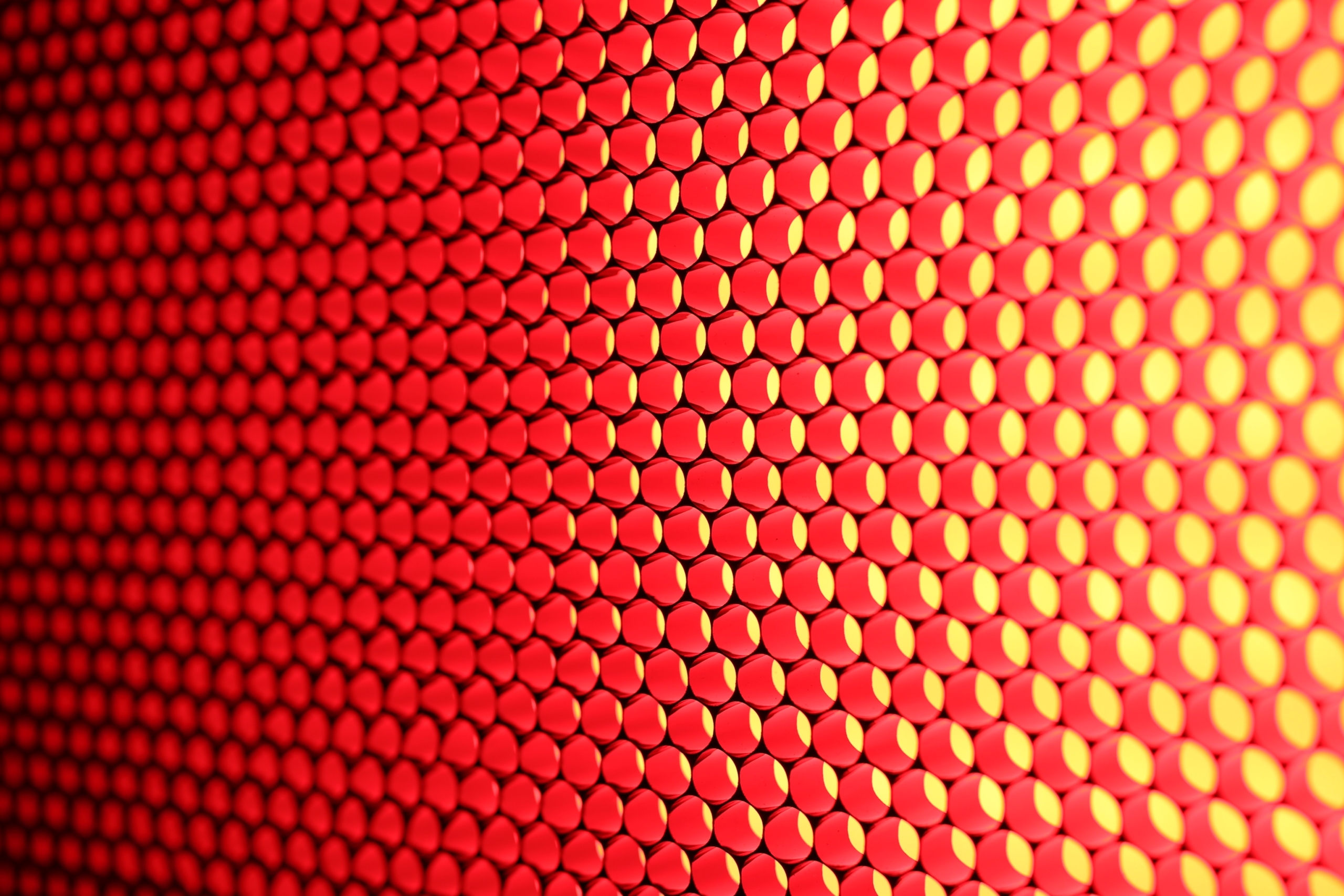 大面積有機フォトダイオードに置き換わる?「シリコンフォトダイオード技術」
大面積有機フォトダイオードに置き換わる?「シリコンフォトダイオード技術」 -

 幸福度を7%上げる「旅行の仕方」
幸福度を7%上げる「旅行の仕方」 -

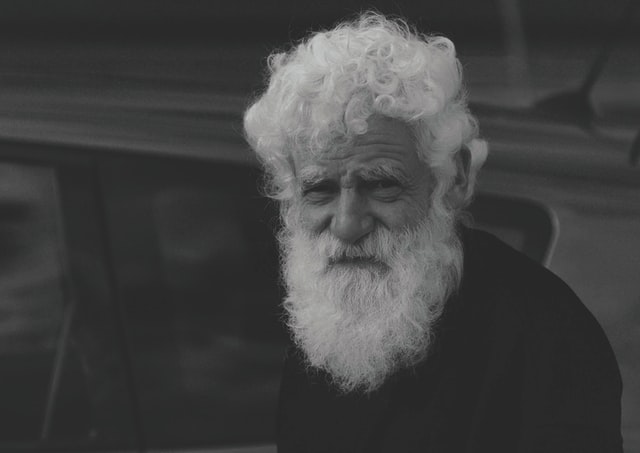 「世界最長寿記録を更新し132歳まで生きる人が出現する」ベイズ統計学予測
「世界最長寿記録を更新し132歳まで生きる人が出現する」ベイズ統計学予測 -

 組織の中で行われたインシビリティ(非礼な言動)を軽視してはいけない理由
組織の中で行われたインシビリティ(非礼な言動)を軽視してはいけない理由
N E W S & P O P U L A R最 新 記 事 & 人 気 記 事
WHAT'S NEW !!
-






男女ともに長生きになる「男女平等」
【男女ともに長生きになる「男女平等」】 権利とは人間が作り出した構造ですが、男女平等が進むと男女ともに長生きになるようです。 The first global study to investi... -






他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く
【他者を犠牲にして利益を取る・利益を度外視して他者への害を取り除く】 他者を犠牲にして自分の利益を選ぶ、自分にとって利益は少ないが他者への害を防ぐ、道徳的なに... -






「寿命を延ばす」良質な睡眠
【「寿命を延ばす」良質な睡眠】 良質な睡眠をとることは、寿命を何年も長くする可能性があります。 Getting good sleep can play a role in supporting your heart and... -




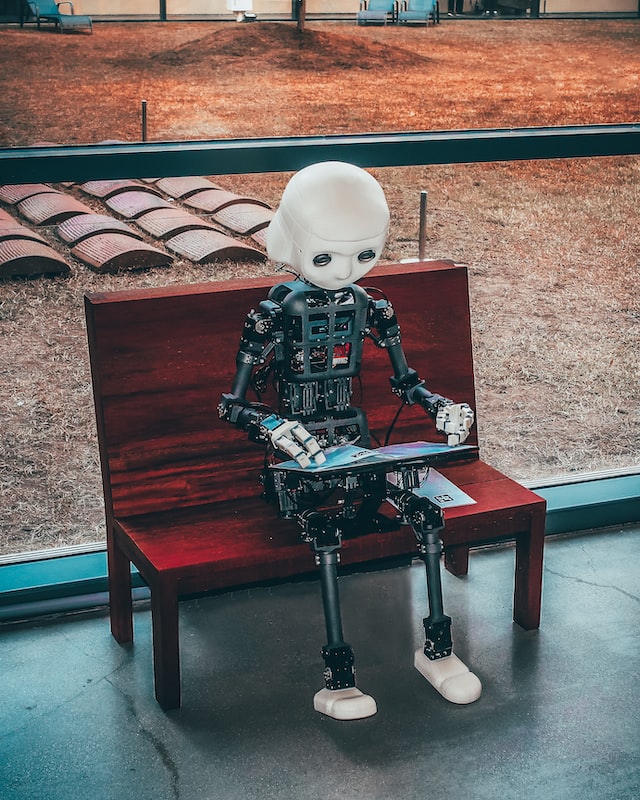
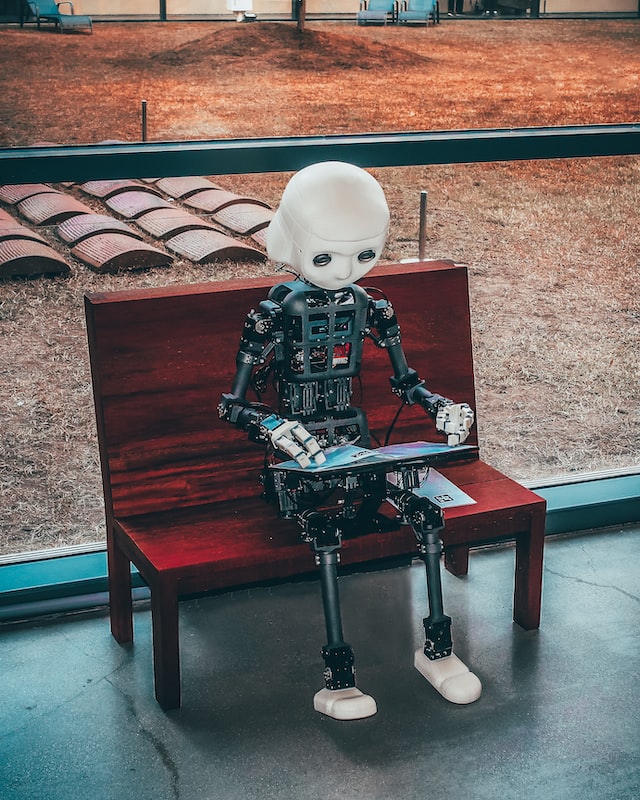
見極める力を養う「チャットボットの精度」
【見極める力を養う「チャットボットの精度」】 ChatGPTをはじめ、チャットボットの精度は人が書いたものかどうかわからない程までの水準になっています。 The most rec...
-






なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか
【なぜタイピングより手書きの方が、記憶に定着するのか】 ノルウェー科学技術大学の研究によると、手書きの方が物事をよく覚えることが判明しました。 様々なコンピュ... -






どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」
【どんな曲が好き?「 音楽の好みと性格の関連性は普遍的 」】 激しい音楽を好んで聴く人は、激しい性格の持ち主なのでしょうか?研究者は、音楽の好みと性格の関連性は... -






視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」
【視覚と意思決定領域の結びつきが強い「鮮明なイメージ能力がある人」】 鮮明にイメージできる人は、視覚ネットワークと意思決定に関連する脳の領域が強く結びついてい...
News
- 新着記事 -
Popular
- 人気記事 -
H A P P I N E S S幸 福
人気 (❁´ω`❁)
M E A L食 事
B R A I N脳
人気 (❁´ω`❁)
H E A L T H健 康
人気 (❁´ω`❁)
-






人体・脳
健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」
【健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」】 ボリビア・アマゾンの先住民族であるツィマネ族が、アメリカやヨーロッパの人々に比べて... -






社会
自制心が健康と若さをもたらす理由
【自制心が健康と若さをもたらす理由】 デューク大学の研究チームは、自制心が心身に及ぼす影響を調査しました。 1000人を出生から45年間に渡って追跡した大規模調査で... -






健康
高強度インターバルトレーニングは、適度な運動よりも心臓を強化する
【心臓を強化する高強度インターバルトレーニング】 ノルウェー科学技術大学の研究によると、トレーニングの強度が、病気の重症度を軽減し、心臓機能を改善し、作業能力...
-






人体・脳
健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」
【健康な脳を保ち老化を遅らせる「アマゾンの先住民族ツィマネ族の生活習慣」】 ボリビア・アマゾンの先住民族であるツィマネ族が、アメリカやヨーロッパの人々に比べて... -






社会
自制心が健康と若さをもたらす理由
【自制心が健康と若さをもたらす理由】 デューク大学の研究チームは、自制心が心身に及ぼす影響を調査しました。 1000人を出生から45年間に渡って追跡した大規模調査で... -






健康
高強度インターバルトレーニングは、適度な運動よりも心臓を強化する
【心臓を強化する高強度インターバルトレーニング】 ノルウェー科学技術大学の研究によると、トレーニングの強度が、病気の重症度を軽減し、心臓機能を改善し、作業能力...
J O B仕 事
人気 (❁´ω`❁)
-






社会
週休4日制で生産を維持する
-






人体・脳
アイデアや閃きが降りてくる「横断的なコミュニケーション」
-






社会
大災害を読み解く鋭い解決策
-






思考・瞑想
賞や表彰が発明家の創造性を低下させる
-






人体・脳
創造的な人はここが違う!「非創造的なハブを回避し非典型的なアプローチをする」
-






社会
アメリカ陸軍で既に多数の成功を収めている「人々を創造的にするトレーニング」
-






社会
2年は普及しない?「カテゴリーイノベーション戦略」
-






社会
管理者級以上必見「創造性を引き出す同僚間の友情とサポートを育む組織づくり」
-






社会
アイデアを創出する人数「少人数のグループのほうが新しいアイデアが出やすい」
-






健康
散った気を元の集中に戻す「1日最大50%費やす迷いを断つマインドフルネス」
-




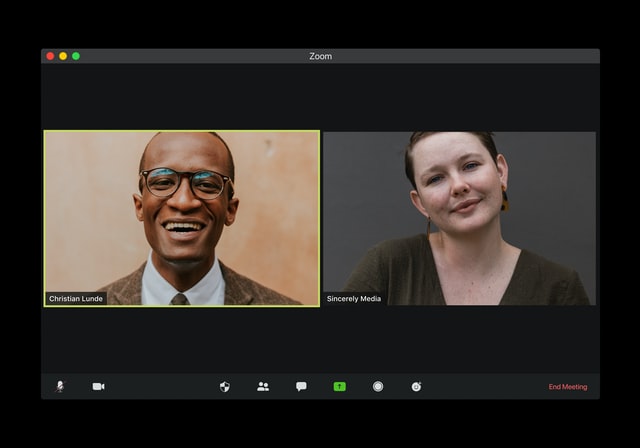
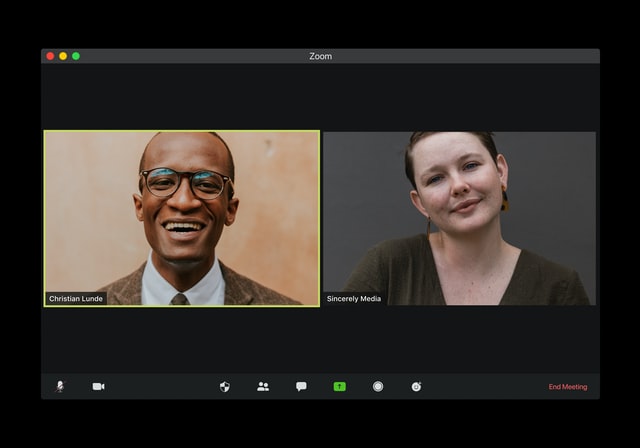
社会
移動によるエネルギーが激減「環境に優しく誰でも参加できるオンライン会議」
-






社会
山火事コスト数十億ドルのコスト削減「インドネシアの泥炭地回復」
-






社会
価格末「99円」設定が販売者に不利益を及ぼす驚愕の理由
-






社会
購買意欲を掻き立てる商品提示方法
-






社会
「感情的異質性」がチームの創造性を高める
-






社会
従業員の創造性を高める驚愕の方法「報酬を選択制にする」
-






社会
テクノロジーの力でセレンディピティを生み出す
-






社会
様々なテーマの問題への取り組みにつながる「ダ・ヴィンチ構想」
-






社会
改善が必要な状況に「やめる」という解決策がでない理由
-






社会
空想が苦手な理由と、その修正方法
-






学習
パズル解きの極意、最良の選択より優れた驚愕の方法
-






社会
大麻が独創的で実現不可能なアイデアを創出するという実験結果
-






社会
記憶に残るユーモアを含んだニュース
-




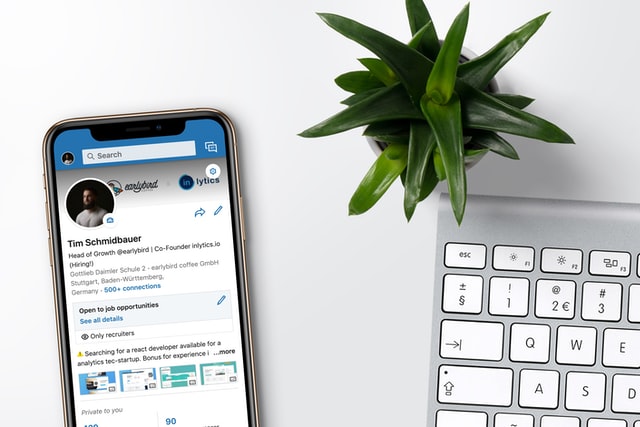
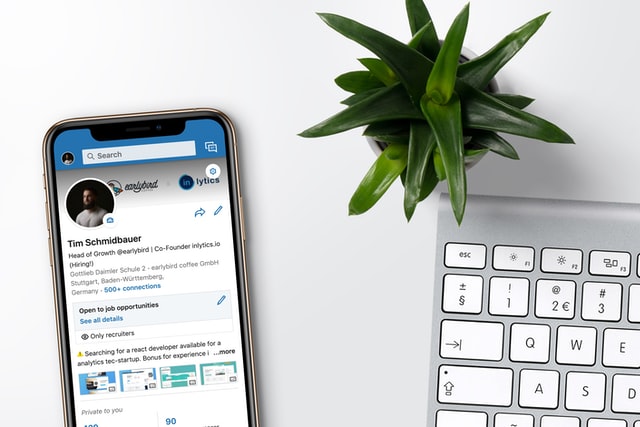
社会
なぜメッセージと画像が一致してない情報は伝わらないのか
-






社会
消費者を購買に結びつける音楽
-






技術
自動化工場などの緊急事態に備えて知識を生かしておく方法
-






社会
「生産性も顧客満足度も向上」プロジェクトに自主性を持たせる
-






人体・脳
人は1日に35,000回の意思決定をしている「意思決定を行うアルゴリズム」
-






社会
他文化と頻繁衝突する文化圏は協力的なゲームが流行?「ゲームからみる文化」
-






社会
「通勤はわるいもの?」モバイルセンシングで仕事の成果と通勤の関連性を解明
-






社会
テクノロジーは労働者の幸福度にどのような影響を及ぼすか
-




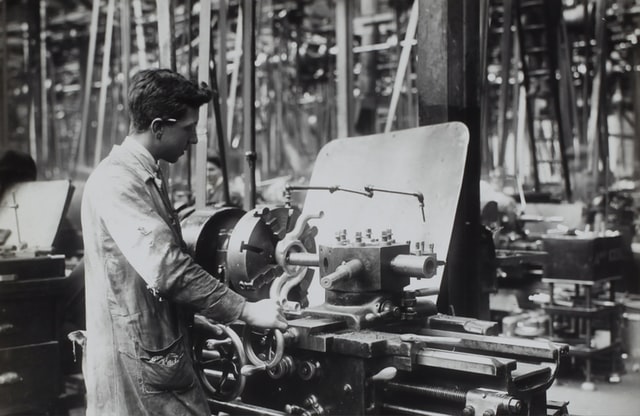
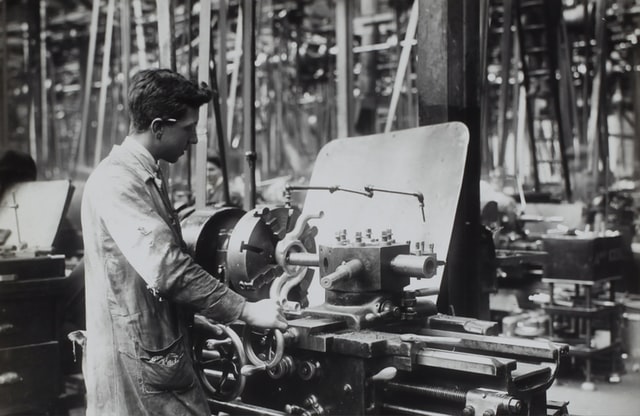
社会
雇用の創出ではなく雇用の置換が進む「ロボットなどの作業の自動化」
-






社会
「柔軟で弾力性のある対応が可能」生物系を模倣した多様なサプライチェーン
-






社会
「患者のメンタルヘルスケアを向上させる」患者と心理療法士のマッチング
-




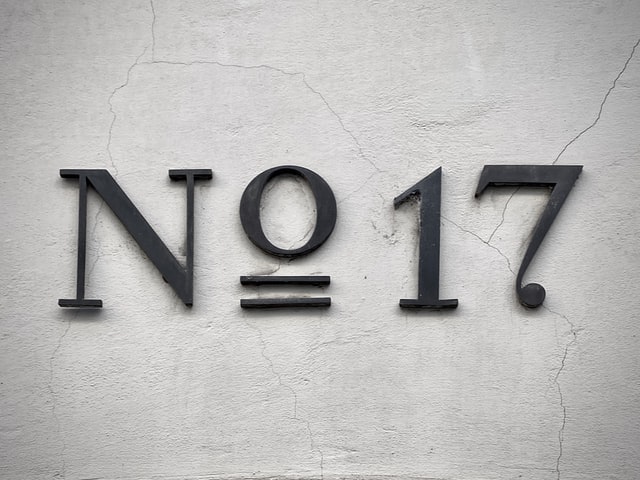
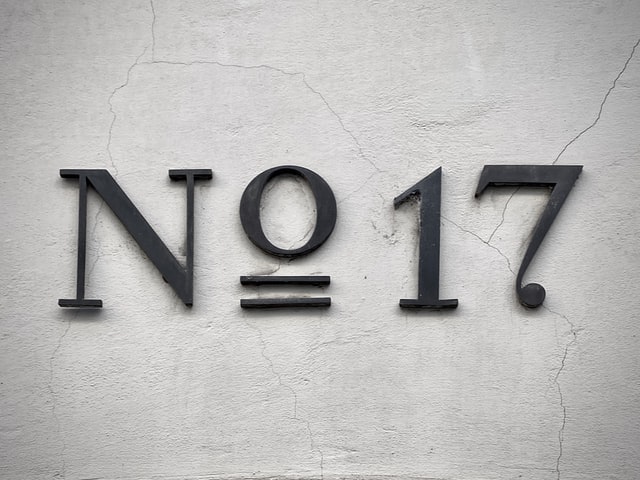
学習
デジタルデバイス用に最適なフォント「AdaptiFont」
T E C H N O L O G Y技 術
人気 (❁´ω`❁)